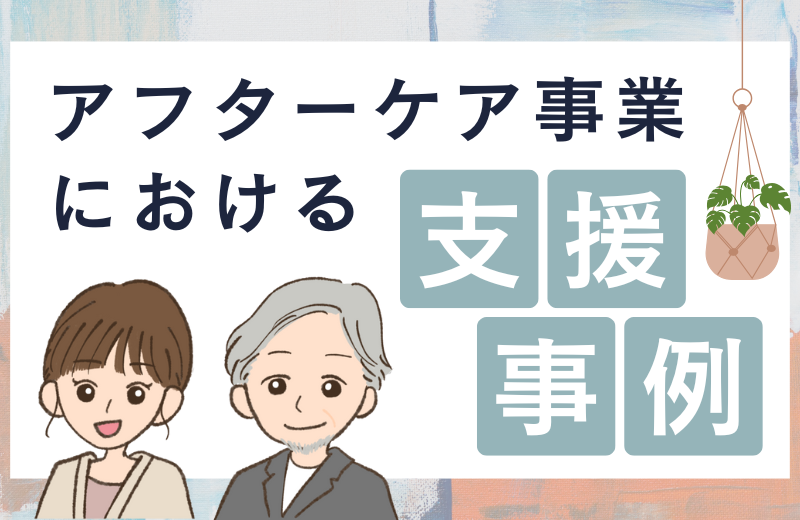社会的養護のアフターケア事業における支援事例【6】〜NPO法人えんじゅのお取り組み〜
投稿日
2022年の児童福祉法改正によって、アフターケア事業の対象者が広がることになりました。
「社会的養護の措置解除者(退所者)」から、「社会的養護経験者“等”」へ。虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった人たちも、事業の対象に含まれることとなりました。
そこで今回は、その変化に合わせて活動を展開されている、社会的養護のアフターケアに取り組む団体で構成する全国ネットワーク「特定非営利活動法人えんじゅ」の理事長 高橋亜美さん、副理事長 矢野茂生さんに、活動の想いや法改正によって変わってきていること、今後の展望などについてお伺いしたお話を全6回の連載形式でお届けしています。
最終回の第6回となる今回は、おふたりが現在のご活動で大切にされている想いをお伺いできればと思います。
様々な背景がある方々を受け入れるにあたって、気をつけていらっしゃることはありますか?
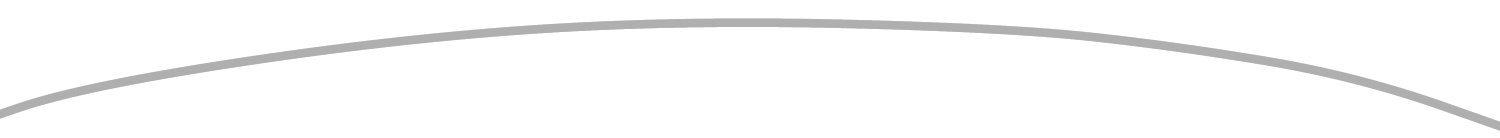
本当に性別、年齢、属性、様々な人たちを相手にしていますが、生きてるのが苦しいっていうのと、被害をかつて受けてきたっていうこと、親や家族を頼れないっていうこと、 その共通点だけはあります。
それで私たちがそれを全部完璧に網羅して対応していくっていうのはもちろんできないので、出会う入り口にはなって、 私たちがいろんな分野の方と仲良くなって助けてもらえるような関係性を作っていくというのが本当に大事だなと思っています。
弁護士さんも学校の先生も、あと病院ですね。精神科医とか産婦人科とかも、それもフェイストゥフェイスで繋がっている、ゆずりはを応援してくれる人や協力してくれる人たちとの繋がりをしっかり作っていくっていうのは、もう欠かせない1つだなっていうのは 思ってます。
あと、本人にも考えてもらうことですね。「こっちが全部やってあげるよ」っていうんじゃなくって、「あなたがどうしたいか」っていうことだったり、全部こっちで手続きしていくんじゃなくて、一緒にやってくっていうスタンスも大事にしています。
私たちもネットワークというか、すぐ相談できる多様な方との関係を作っていくことはずっとやってきたことです。
あとは背負いすぎないっていうのも、大事ですね。
相当な被害を受けた人たちが相談に来るので、昼夜問わず電話してくるとか、メールしてくるとか、ものすごい言葉を投げつけられたりもあるから、そこで振り回されないという、潔さみたいなのは大事です。
私たちも寝る時間必要だっていうのとか、安心な関係を作ってくのに、「そんな言葉言われたらもう話したくない」とか、そういった距離感とか、線引きとか「あなたが苦しいから、あなたが誰も頼れないから、どんなあなたでも私たち応援します」っていうスタンスじゃないっていうこと、やっぱり そこにお互いの配慮とか、その辺のやりすぎないっていうところで踏ん張るみたいなところもすごい大事にしてますね。
そして、仲間ですね。ゆずりは内でのチームワークっていうのは本当に大事。1人で立ち打ちできないような人が多いので、高橋亜美が 1人であなたの話聞いてきますとかじゃなくて、ゆずりはとして応援していくよっていうスタンス、そういった共通認識みたいなのは、10人にも満たないスタッフ数なんですけど、スタッフ数が少ないからこそ、共通認識もぐっと深く強く持ちやすいっていうのもあるかなと思ってます。
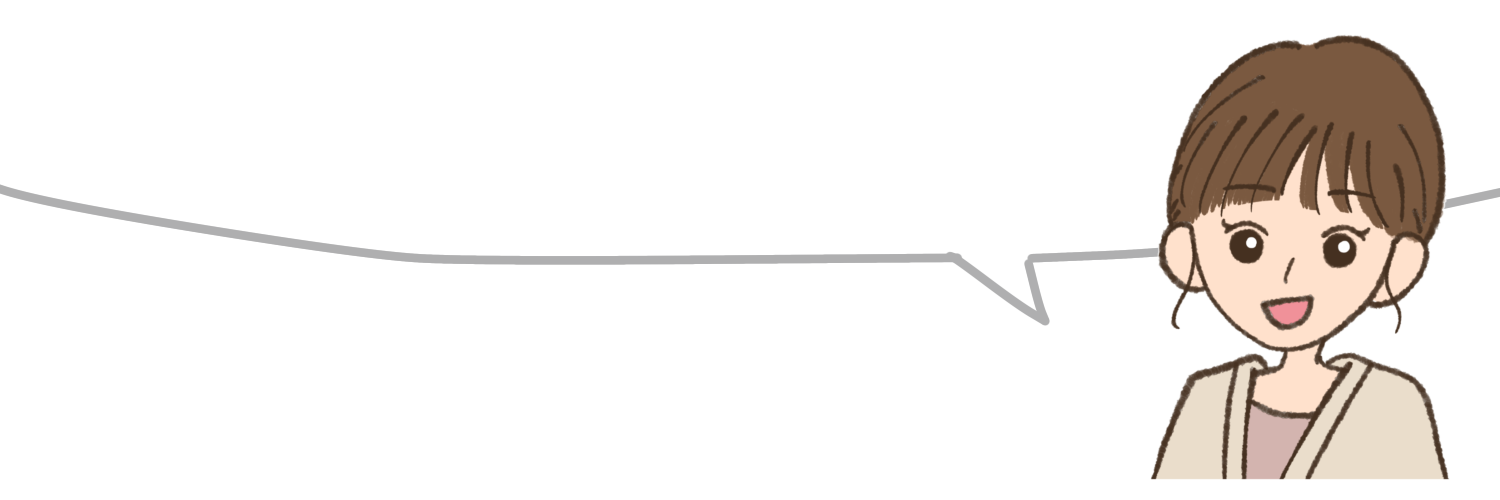
ありがとうございます。
いろんな支援を専門にしている方々との繋がりの中で、こっちに繋いで、 そこがどうなっていくかっていうのを見守るっていうのもすごく大事ですね。
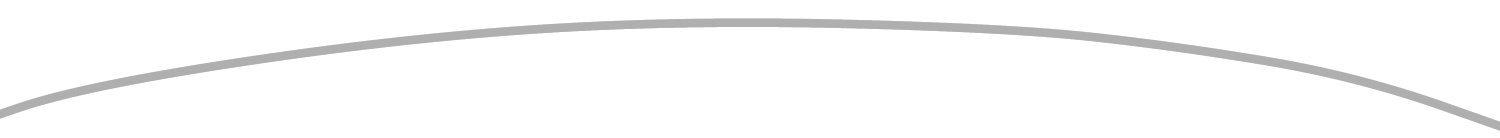
私たちはもう「出会ったが最後」みたいに言ってるんですよね。
はじめは何歳までみたいなあったんですが、とりあえず今住居持ってたら大丈夫ってなっても、また生活していく中で困ったこと起きてっていう、何度も何度も相談があるから、「もういいや、もう一生で」っていう感じで。
それで、その都度やれることを探して、「 ごめん。何もアイデアないな。」みたいな時があってもよくて、一緒にしんどいを言える場所があるっていうのもいいかなって思ってはいます。
間口を広げておく、扉を開けておきたいです。 私たちは、相談してくれた人たちと一緒にやってきた。苦しいと言ってくれる人がいなかったら、制度化もされなかったし、私たちも働き続けることができなかった。
一緒により安心して生きていけるための仕組みを、たどりついてくれた人たちと一緒に作っているような感じでやっています。 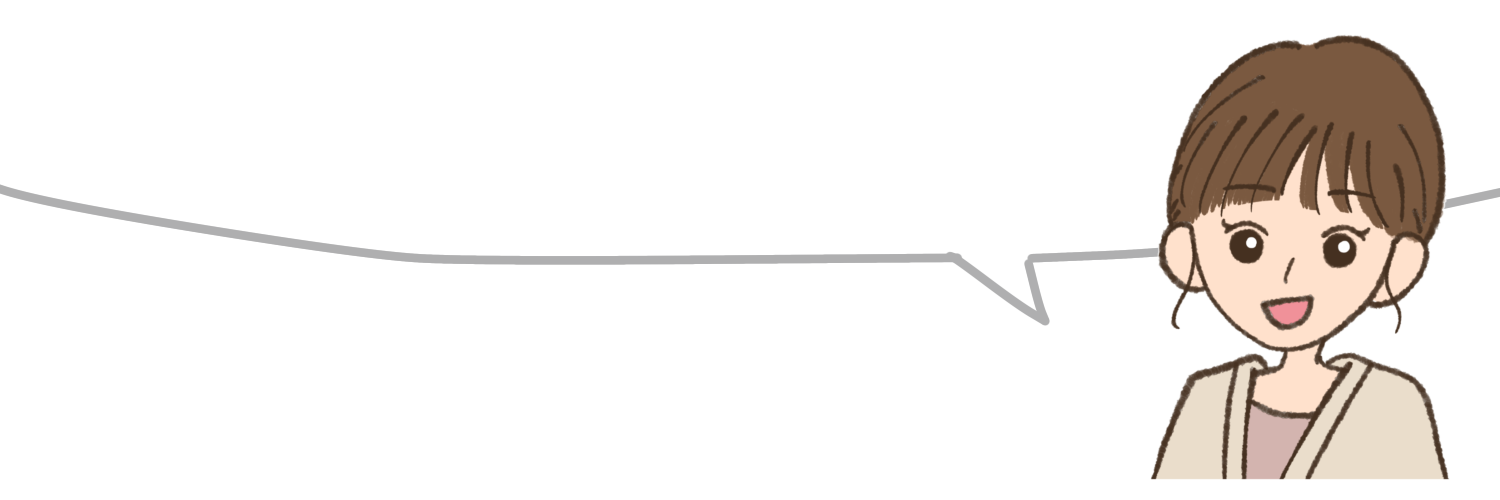
高橋さん、矢野さん、お取り組みについてお聞かせいただきありがとうございました。
sureでも子どもの育ちや自立を支援するための研究を続けておりますので、その観点でもとても大切にしたい、本質的なお話を伺うことができました。
社会的養護やアフターケアも含め、1人ひとりがより社会に参加していく支援ができるよう、sureでも引き続き自立支援を考えてまいります。