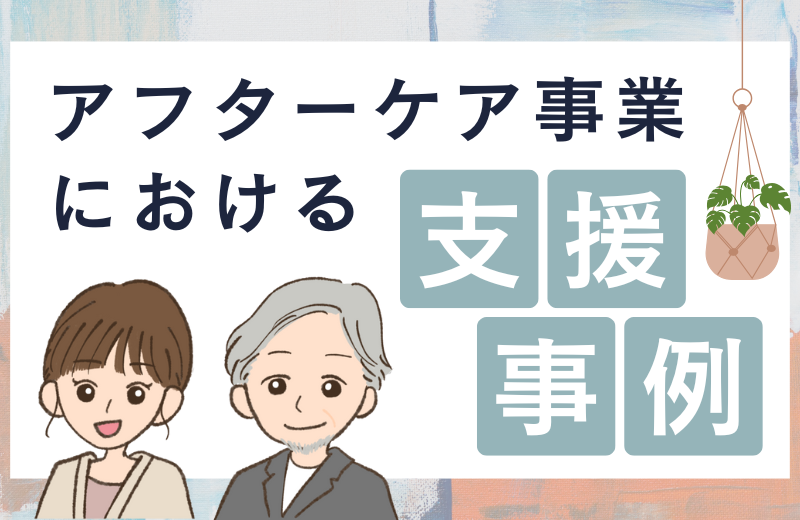社会的養護のアフターケア事業における支援事例【1】〜NPO法人えんじゅのお取り組み〜
投稿日
2022年の児童福祉法改正によって、アフターケア事業の対象者が広がることになりました。
「社会的養護の措置解除者(退所者)」から、「社会的養護経験者“等”」へ。虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった人たちも、事業の対象に含まれることとなりました。
そこで今回は、その変化に合わせて活動を展開されている、社会的養護のアフターケアに取り組む団体で構成する全国ネットワーク「特定非営利活動法人えんじゅ」の理事長 高橋亜美さん、副理事長 矢野茂生さんに、活動の想いや法改正によって変わってきていること、今後の展望などについてお伺いしたお話を全6回の連載形式でお届けします。
第1回の今回は、おふたりそれぞれに活動内容についてのお話をお伺いします。
ー高橋さん、矢野さん、どうぞよろしくお願いいたします。まずは矢野さんのご活動についてお伺いできますか?
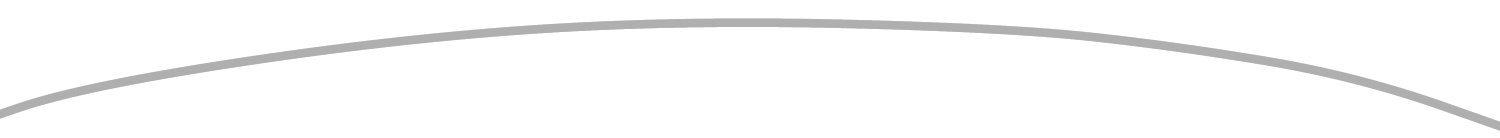
僕は大分県で「特定非営利活動法人おおいた子ども支援ネット」という法人で社会的養護の拠点事業を行っています。
実は僕も元々前職は児童自立支援施設に勤めていました。今からちょうど10年前に退職をして作った法人です。
その法人を作った経緯としては、福祉の事業にはスペシャルで専門的な福祉もありますが、もう少し生活の中に溶け込んでいくような、多様な方が参加できるような福祉の事業も大事だと感じていました。
僕も児童自立支援施設にいましたので、特定の対象を切り取ったような福祉事業というのは、やはり社会からかなり見えにくいと思っていました。
社会から見えにくいからデータも集まりにくいし、参加者も少ないし、いわゆる「いいイノベーション」は全然起きないんです。
ですからそういった文脈で考えた時に、僕たちがいろんな事業をなるべくスペシャルで行っているのは、うちの中では児童発達支援センターくらいかなと思います。
ただ、児童発達支援センターにも家族を全部巻き込んで、家族も一緒になって入ってこれるようなセンターを作ったんですよね。
そう考えた時に、アフターケア事業は、高橋亜美さんの背中を見ながらいろんなこと学ばせてもらいながらやっていますが、元々子ども若者総合相談センターや引きこもり地域支援センターなども一緒になって一体的にやっていますので「最初から対象をくくっていない」というのが僕たちの法人の活動なんです。
社会的養護の文脈で言うと、いわゆるケアリーバーと言われる退所者が同じ属性を持って集中的に集まっていくという取り組みも大事ですが、 ケアリーバーさんたちがいわゆる違う形のいろんな若者と交わっていくことも大事だと私たちは思ってまして。
なので、制度事業をやりながら「属性に偏らない事業をどう作るか」というのが、僕らの1つのセンターピンですので、いろんな方が元々なんでも来てるみたいな雰囲気なんですよね。
だから、その中でどんな人も来ていて、お互いにいろんな困り感は持っているけど、お互いに支え合うこともすごく大事だし、僕らが100パーセント全部できるわけでもないですし。
なので、みんなで多様な方が集まって、その中でどういった活動が必要かということをちょっとずつやってるような取り組みをしています。
就労の支援や学び直しの支援、家族の調整、企業さんとの調整、本人の生活のスキル、生活支援の部分など、 そういったものを必要な時に必要な人ができるだけオープンにやっていくというところを心がけております。そんな感じの事業体です。
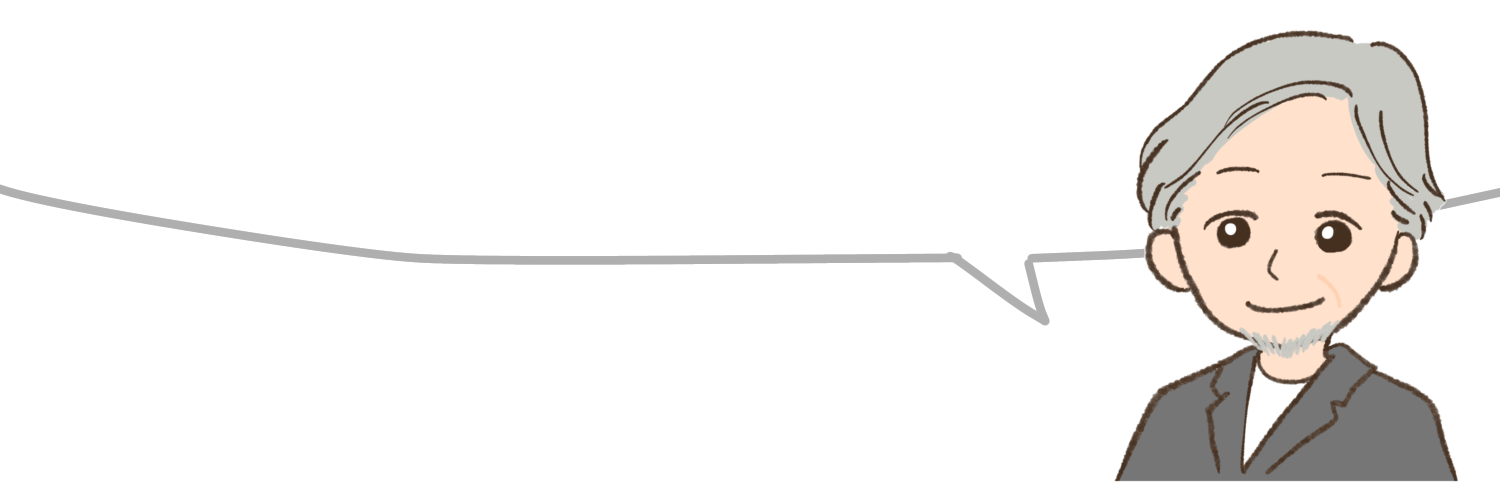
ー矢野さん、ありがとうございます。
線を引かないという点がとても特徴なのかなとお伺いしていて感じました。それでは高橋さんからもお話を伺えますでしょうか?
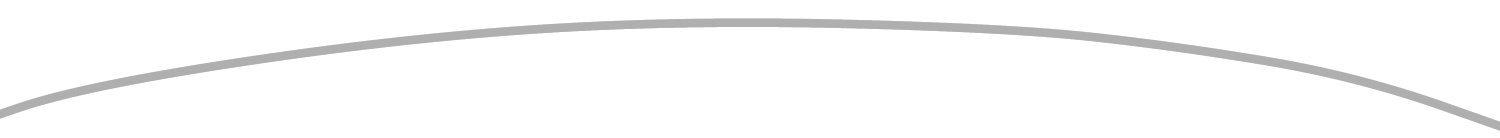
ではまずゆずりはがやっていることをご紹介します。
今、開所して14年目で、私は自立援助ホームの職員をしていました。
それこそ自分が一緒に暮らしてきた子たちがホームを出て1人暮らし、住み込み、就職していく中で困難な状況に陥ってしまうっていうのを目の当たりにしました。
そこでまず、自分のホームを出た子たちに対して、住む場所が変わるだけで引き続きずっと関係は続いていくし、苦しい時こそ相談してほしいっていうような取り組みを積極的にしていくようになりました。
そうするとうちのホームを巣立った子以外の「困った子同士ネットワーク」で、その子の相談にも乗ってあげて、連れてくる子たちがやっぱり社会的養護を経験した人で、自分の施設にいろんな事情があって相談できないっていう人たちにも多く繋がったりしました。
そしてちょうど15年ぐらい前に東京都で初めて退所者調査が行われて、その時のいろんなデータが衝撃的だったんです。
退所して10年間の子たちの追跡を行ったのですが、施設や里親さんとの関係でメールアドレスも電話番号もわからないという状況になっているのが半分以上あり、こんなに簡単に繋がりが「どこに住んでるかもわからない」なんて状況になっちゃうんだっていうことがショックでした。
いろんな事情で、施設や里親さんに相談できない子たちの相談場所を作りたいという思いで、ゆずりはを社会福祉法人「子供の家」の元で開所してもらいました。
実際やってみると、相談にたどり着いてくれる人たちというのが、社会的養護を経験した人だけでなく、施設に保護されたことは1度もないけれど、ずっと家庭で苦しい思いをしてきたとか、あるいは一時保護所だけでもう戻されてしまったっていう人たちの相談ももう開所時から多くありました。
そして社会的養護を入り口にしてだったり、今虐待を受けているわけじゃないけど、子ども期を安心して暮らせてこなかった、苦しい思いをして生きてきた人たちが、ゆずりはに相談してくれるようになりました。
社会的養護でカバーしきれなかった人たちが、私たちのところに相談来てくれて、それを断るわけにもいかないというのがあって、もう開所時から「しんどいやつ集まれ」状態で、断ることをせず受け入れてきました。
相談者も10代後半からは60代ぐらいまで幅広くいて、年齢層は20代〜30代の方が1番メインで多いかなと思います。
ゆずりはも矢野さんのところと同様に、属性で括らない、括れないという感じです。
社会的養護かどうか、男性か女性か、年齢がいくつかで、対象者を条件で括らないので、もう本当「ごった煮」です。
性別も年齢も、 社会的擁護経験有無も、障害者手帳持ってたり持ってなかったり、色々なんだけど、ともかく全ての相談者の人に共通しているのは、親や家族を頼ることができないっていうことと、安心して子ども時代を暮らせてこなかったっていうことは共通しています。
やっていることは、生活保護の申請とか、 住所をブロックする支援措置の手続きとか、アパート借りる身元保証人になるとか、個別の対応をそれぞれやっていきます。
その他に、 本当小さい場所なんですけど、ゆずりはの拠点場所を使って集える場所だとか、高卒認定の学習会とか。
また働きたいけど働くことができないという人たちもとても多いので、就労支援って言ったらいいのかな。「一緒に働こうぜ。」みたいな感じで、ジャム作ったりもしています。活動内容としてはそんな感じです。
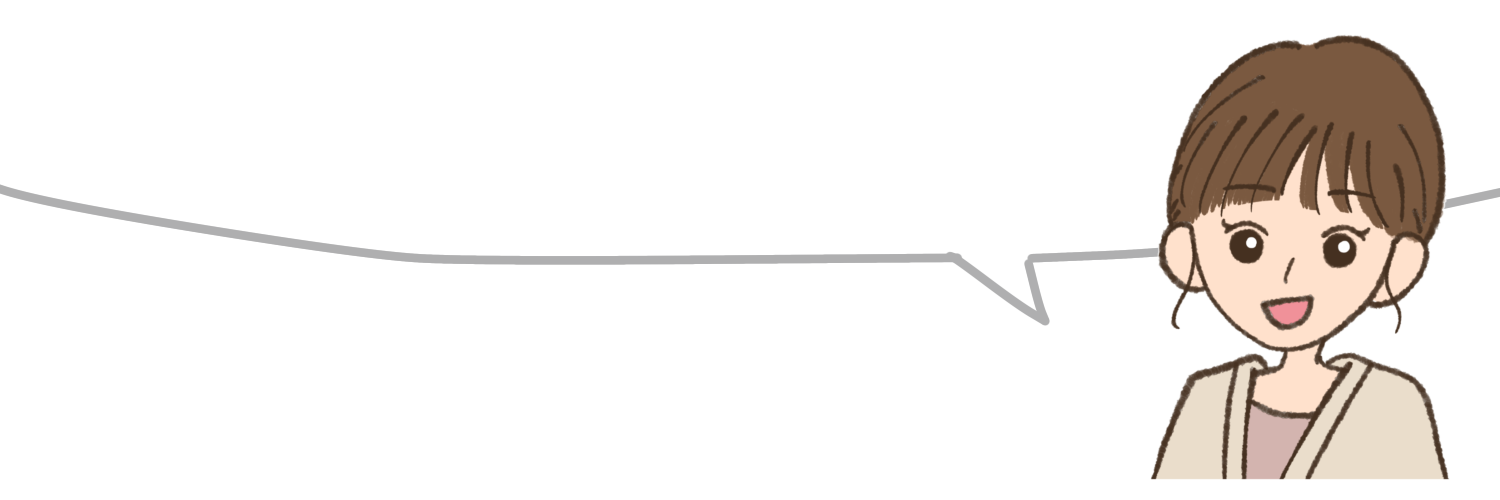
高橋さん、ありがとうございます。
次回は、社会的養護のアフターケアに取り組む団体で構成する全国ネットワーク「特定非営利活動法人えんじゅ」で行っていらっしゃる活動について、具体的なお話をお伺いしていきます。どうぞお楽しみに!